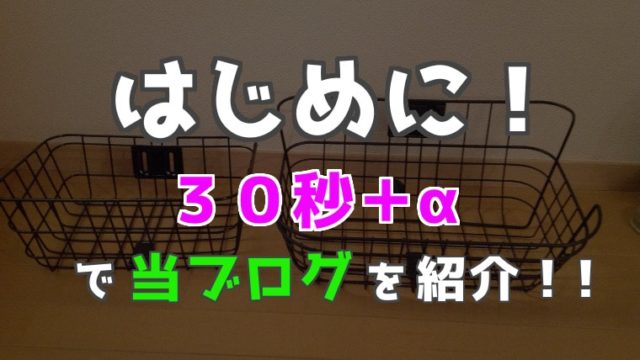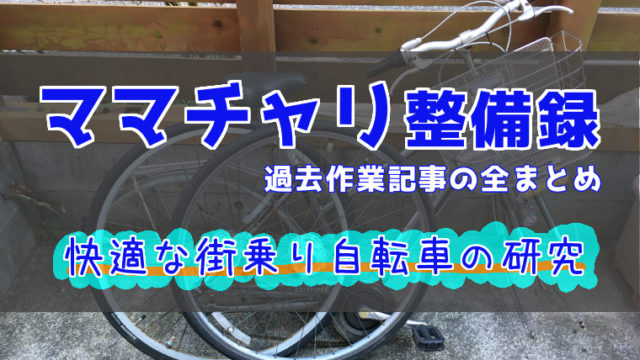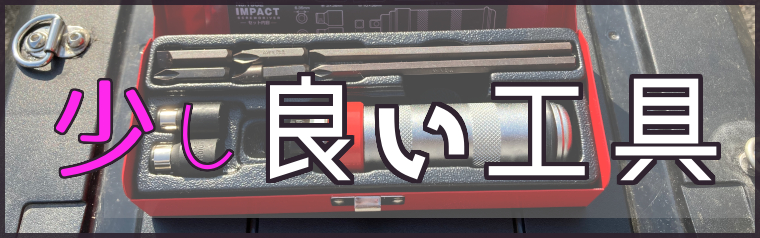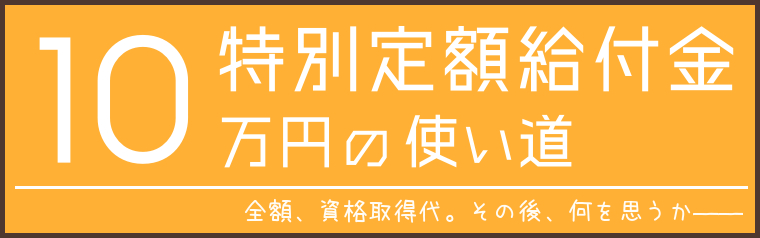ママチャリ(シティサイクル)後輪ブレーキに多用されるローラーブレーキの観察と、グリスアップについてです。
自転車のブレーキというと、『ブレーキシュー2つでホイールを挟み込んで減速させる…』なんてイメージを持ちますよね(自分だけ?)。しかし、ママチャリ後輪の場合、ローラーブレーキと呼ばれるものが使用されることがあります。
私が所有するママチャリ4台、すべてローラーブレーキが装備されています。でも、ブレーキシューもないのにどうやって止めるのかな?というのは長年の疑問でした。
今回、ローラーブレーキ周辺からキーキーという異音があったこともあり、観察も兼ねて整備(グリスアップ)をしてみることにしました。
この記事の内容
- ママチャリのリアブレーキがキーキーうるさい
- ローラーブレーキの観察
- ローラーブレーキのキャップの交換
ローラーブレーキ(インターM)のグリスアップ
異音や急ブレーキがかかったら、グリスアップのサイン
4台所有する自転車は整備前、どれも後輪のききが悪い気がしていました。
例えば、16年ほど前から乗っているアルベルトは、やたらブレーキがかかりますし、下り坂でブレーキをかけるとキーキーと異音がします。
今回、シマノ ローラーブレーキグリスという専用品を用意したのですが、付属の説明書にグリスアップのタイミングについて以下のような記載がありました。
- ブレーキをかけた時、異常に急ブレーキがかかる
- ブレーキをかけた時、異常音がする
SHIMANO ローラーブレーキグリス説明書より
まさに表記にある状態ですね。アルベルトほどではないにせよ、他の3台の自転車も似たような状態です。整備の頃合いとしてはちょうどよかったのかもしれません。
ローラーブレーキのグリスアップ方法

実際に自転車後輪に装備されているローラーブレーキにグリスを注入してみます。私の自転車にはすべてSHIMANOのインターMというブレーキが装備されていました。
ピンクで丸した部分にキャップが付いているのでこれを外します。固い場合はマイナスドライバーなどで引っかけるといいです。大体は指で取れると思います。

キャップが外れました。キャップは非常に小さいので紛失しないようにしましょう。

注入口からグリスを入れていきます。
今回、用意したグリスはシマノ ローラーブレーキグリスです。中身の色が真っ黒で今まで見てきたグリスとはまた違う感じがします。
ちなみにローラーブレーキのグリスアップは、自転車屋さんでも数百円でやってもらえます。中々使わないグリスを無理して在庫抱える必要もないですから、お願いするのも一案です。

ローラーブレーキグリスは購入当初は封がしてありますので、容器の先端をハサミで少しだけカットして、使える状態にします。
カットしたノズルの先端を、先ほど開けた補給口に12mm以上突っ込んでグリスアップを行います。この時、後輪をゆっくり回しながら補給するようにとSHIMANOの説明書にありました。
ローラーブレーキの説明書にはグリスの適量がどの程度かという説明がありませんが、SHIMANOのHPよりディーラーマニュアルを見ると5gが適量とのことでした(*1)
購入したグリスは100gですから、5g使用するとして約20台分あることになります。1本持てば、自転車人生一生分でしょうか。笑
ただ、正確に5gというのは難しいのである程度勘にはなりますが、グリスアップ→試走を何度か繰り返して違和感がなければオッケーとしました。
実際、恐る恐る何度かやっていると途中でブレーキのかかりがスムーズになり、異音が解消されることが分かりました。こんなにしっくりくるのか!と驚きます。笑
グリスアップ自体はこれで終了です。手もほとんど汚れませんし簡単なのが良いですね。
ローラーブレーキ インターMのキャップ交換
インターMのキャップ劣化が気になっていた

今回のローラーブレーキ観察中の話ですが、アルベルトに装備されていたインターMのキャップが劣化で破損していることに気がつきました。
写真のように16年前のアルベルトのキャップの色は白なんですよね。周りの自転車をみると最近のものは黒色です。

キャップを観察してみると、横にヒビが入っていますね。少し力を入れると割れ目が広がってしまい、あと何度かキャップの開け閉めをしたら割れてしまいそうでした。
こんなの単品で販売されているのかなあ…と思いながらネットで検索をしてみます。

結論からいうとキャップの販売はされていました。
しかし、少しややこしいのが16年前のアルベルトのキャップは白色でキャップの内側に切れ込みがあるんですよ。写真右側のものです。
対して写真右側が最近の自転車についていたインターMのキャップです。アルベルト以外はこの黒いタイプでした。ちょっと形状が違いますよね。
せっかくなら同じものがいいなあと思いつつ、探してもないんですよね。

そんな中で、シマノ BR-IM31-F グリス穴キャップという商品(写真左)を見つけて購入してみました。切れ込み入っていて似てません?
でも、切れ込みのあるツメの部分がなんだか短い。質感もちょっと固いんですよね。これはなんか違う気がする…。
今思うと型番のBR-IM31-Fがフロント用って意味だったのかな?という気がします。

取りあえず実際にはめてみることにしました。少し固いですが付くには付くのでOKとします。
キャップ選びの正解は現行?インターMの黒いキャップ(シマノ グリスホールキャップ)を購入して付けることだったみたいですね(^^;)
ローラーブレーキ インターMの観察
今回はせっかくのいい機会なので、インターMがどのような仕組なのか、分かる範囲で観察をしてみることにしました。

ローラーブレーキの取り外しは自転車よりホイールを外してから行います。ホイールの外し方は以下の記事にまとめてあります。

ホイールが外れたら、17mmのレンチを使用してピンク丸部分のナットを取り外します。

取り外したローラーブレーキです。
ブレーキのアームを緑色の方向へ引くと(本来ならインナーケーブルがその役割をします)中心のカムが回転します。
すると連鎖的に外側に付いている無数のローラーも押しあがり、ブレーキシューを押し上げ制動するという仕組みのようでした。
グリス穴も示してみましたが、ピンクの丸部分あたりに広がっていくイメージかな?

制動の仕組みは何となくイメージがつきましたが、最終的にドラム部分に接触するシューの部分はどうなっているんでしょう?
スポーツ自転車やママチャリの前ブレーキのようにゴムのようなものが入っているのでしょうか。みるからに金属のパーツしかないので疑問に思い調べてみることにしました。
分解・構造についてはサイクルショップはたの様のローラーブレーキのページが大変参考になりました(*2)
ページを参考にさせて頂くと、やはりローラーブレーキは金属の組み合わせで構成されており、ゴム製のシューは入っていないことが分かりました。つまりグリスが切れた状態では金属同士をぶつけ合って制動している乱暴な状態になります。
その状態では急ブレーキや音鳴りなどトラブルが発生するわけです。グリスアップの大切さがよく分かりますね。
そしてローラーブレーキグリスについては、あちゃぴーの自転車通勤様のローラーブレーキ 分解&グリスアップにも“ローラーブレーキ専用グリスには摩擦材が含まれている”という興味深い内容がありました(*3)
この記事をみて、ローラーブレーキは専用のグリスを徹底させる理由が分かった気がしました。ローラーブレーキのグリスは他と違い、どうも潤滑という意味だけではなさそうです。
グリスが切れていたり、摩擦材がない他社製品を使用した状態というのは、前ブレーキでいうところのブレーキシューが削れて金属部分とホイールをこすり付けている状態でしょうから、いかに危ないかということが想像できますね。
まとめ
以上、ローラーブレーキのグリスアップや劣化したキャップの交換作業についてでした。
作業自体はグリスさえ用意できればどなたでも簡単に行えます。ただ、この専用グリスがなかなかお目にかからないんですよ。店舗で探そうとすると少し苦労するかもしれません。
以前、東急ハンズの自転車コーナーに置いてあってさすがだな~と思いました。急ぎでしたら、インターネット通販が楽だと思います。
今回は長年謎だった後輪ブレーキの仕組みが理解できてとても満足しています。
前輪ブレーキのようにホイールを挟み込むわけでもなく、どうやって止まっているのかなあなんて思っていたのですが、本当によく出来ていますね。
グリスさえきちんと補充できていればほとんどメンテナンスが不要というのもママチャリ向きだと思います。構造上、天候も気にしなくて良さそうですしね。
しかし、ひと手間かけてそのグリスアップをどれだけの人がやるのかという話です(笑)私予想ですが、恐らくママチャリ人口の5%もいない気がします…。
参考にしたサイトや文献
*1 SHIMANO | ハブローラーブレーキ(pdfファイル)
*2 サイクルショップはたの 自転車屋の修理日記 | ローラーブレーキ
*3 あちゃぴーの自転車通勤 | ローラーブレーキ 分解&グリスアップ

クロスカブ本体の改良
本体(JA45)購入 / 外装カバーの着脱 / リアキャリアの拡張 / リアボックスの追加【リアキャリア延長による加工も】 / ホムセン箱の改良(ボルトやフックの増設) / マルチマウントバーの増設 / スロットルアシスト / ナンバープレートに荷掛けフックを追加 / 2ポートUSB電源 / バーエンド着脱とスロットルパイプの交換 / グリップヒーター取り付け / サイドバッグサポート / パニアバッグ取り付け / 右サイドスタンド / エアバルブ角度の変更 / テールランプのLED化 / エンジンオイルの交換 /
クロスカブまわりの道具
身に着けるもの(ヘルメット、ジャケット、手袋etc…)
ヘルメット選び【SHOEI Z7】 (ヘルメット選び方) / グローブ3種【夏・春秋・冬】 / バイクジャケット / 脊髄プロテクターの追加 / ニーガードプロテクター / トレッキングシューズ / レインウェア