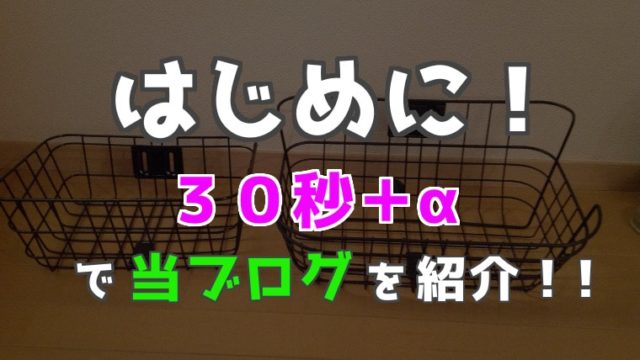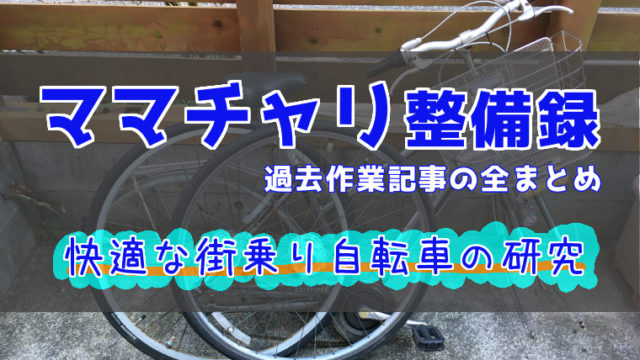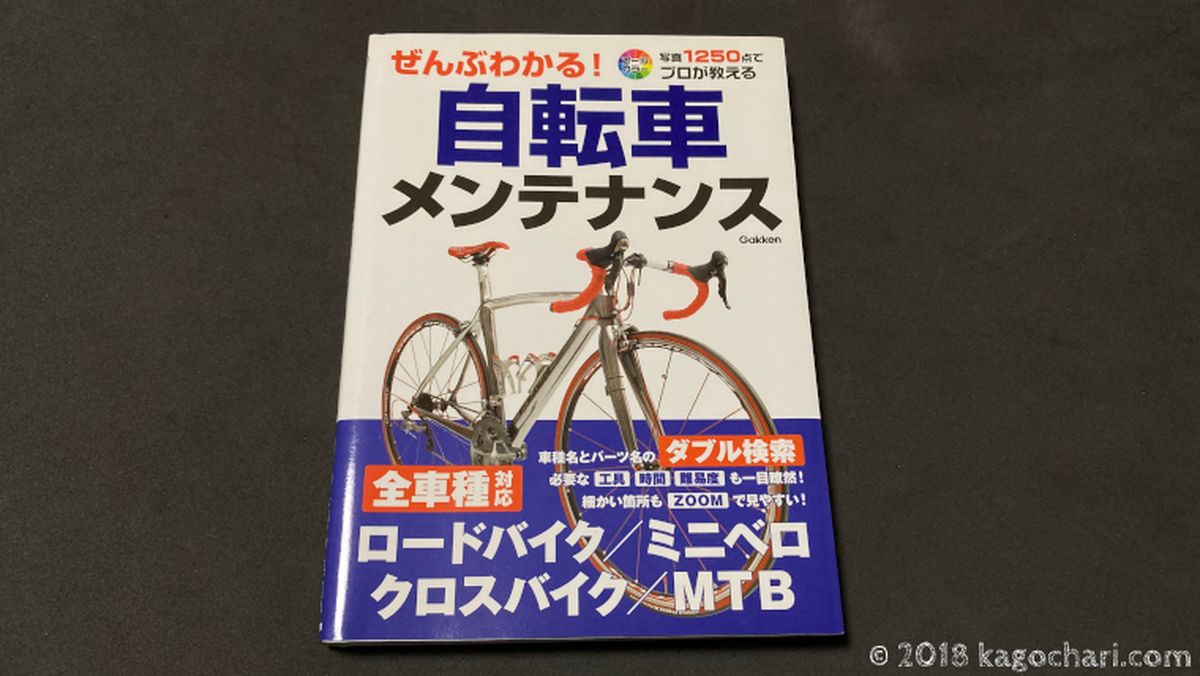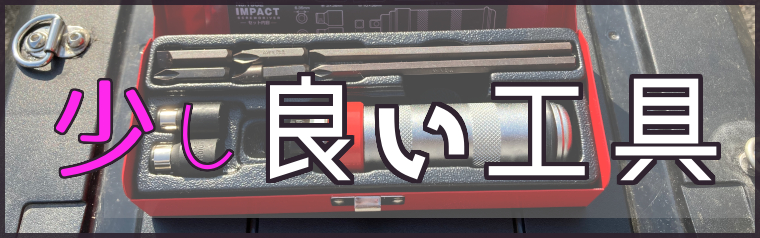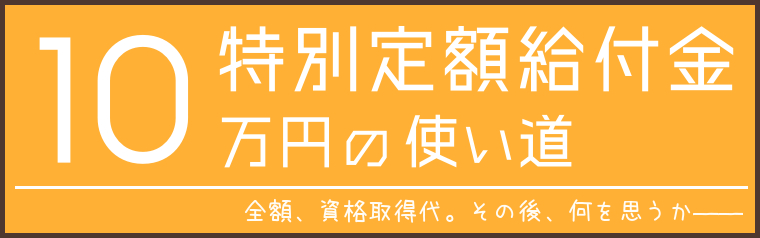今回は紙の本の良さについて、自転車メンテナンスの本を例に書きます。
私は何かを学ぶ際に最低1冊は手元に紙の本を置くようにしています。それは主に以下の3つの理由からです。
- 体系的に学ぶことができる
- 自分の中で1つの判断基準ができる
- 知らない情報に触れやすい
近年、インターネットの発達で情報を手軽に得られるようになりました。実際、私も活用します。しかし、学びの初期段階では本の強みが出やすいとも考えています。
この記事を通して少しでも紙の本の良さを伝えられたら、と思いました。
自転車メンテナンス用の本を紙で持つよさ
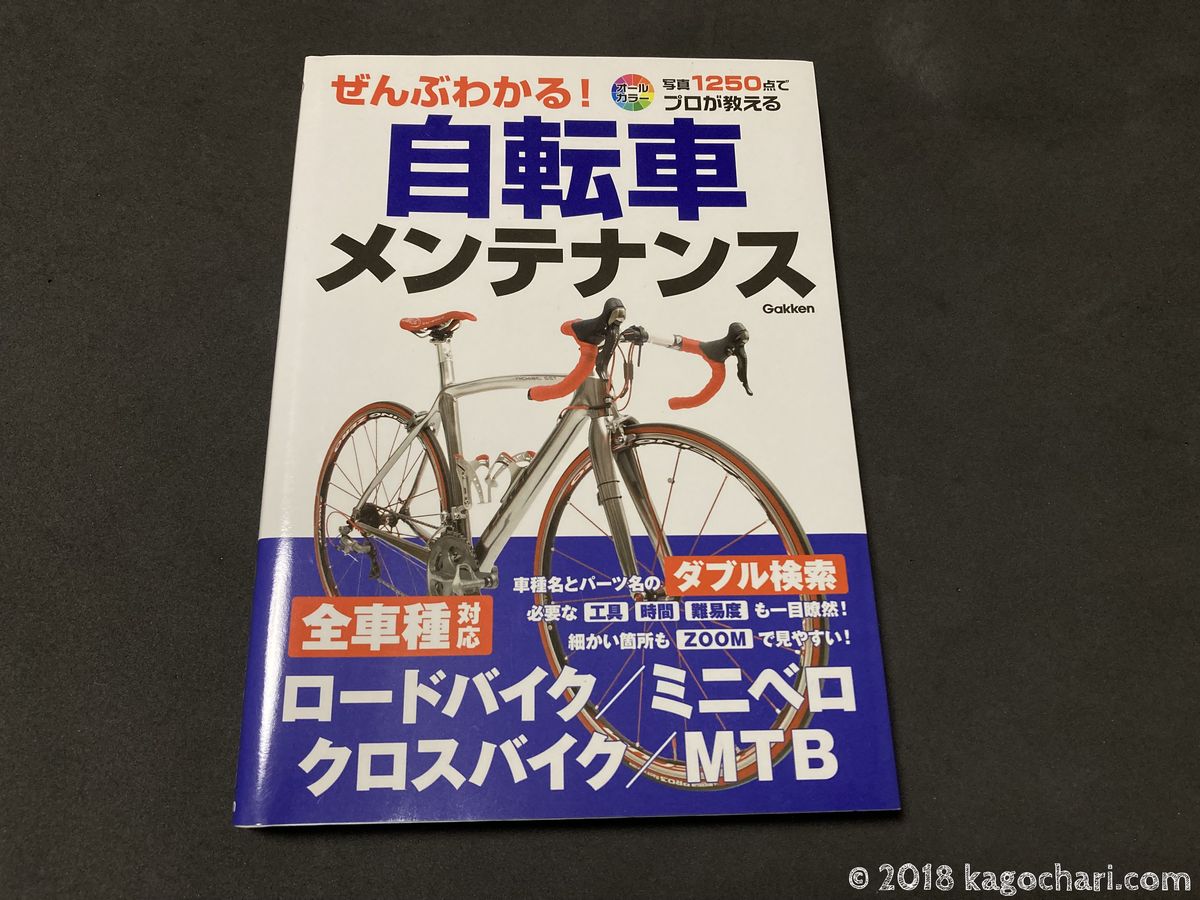
まず、私が自転車メンテナンスの本として所持しているのは、ぜんぶわかる!自転車メンテナンスです。
プレシジョントレッキング(プレトレ)という自転車を購入し、整備をはじめた頃に購入しました。

この本も踏まえつつ、冒頭でも触れた紙の本を持つ3つの利点について書きます。
利点1.体系的に学ぶことができる
まず、本を持つ利点の1つ目は、内容を体系的に学ぶことができるところです。
本というのは、はじめから終わりまでの構成がよく考えられています。本一冊を通して読むことで、その全体像を掴むことができます。はじめのうちはこれが大切です。
例えば、私の所持する本の目次は以下の通りです。
- 自転車の基本
- 工具・ケミカル
- トラブルシューティング
- ポジション調整
- 洗車と注油
- タイヤ・ホイール
- ブレーキ
- 変速調整
- ペダル・チェーン
- サスペンション
- 自転車用語辞典・索引
―ぜんぶわかる!自転車メンテナンス 目次より引用
自転車メンテナンスの基本が詰められています。この1冊を読むことで自転車メンテナンスのおおざっぱな全体像を把握することができますね。
また、構成の流れにも注目で、順番に読むと自転車の大きいところ(自転車の基本)から細かい部分(細かい調整方法)へと読み進んでいくことができるようになっています。
私は物事を理解するうえで、大きいところから小さいところという流れを大事にします。
生物の教科書を思い浮かべてほしいのですが、まず植物という大まかな存在を知り、植物を構成する器官を学び、器官をつくる細胞、細胞の中にある遺伝子…というように大きいところから小さいところへ進みましたよね。
このような流れを把握しやすいのは本の強みです。これは初期の学びを助けます。
利点2.自分の中で1つの判断基準ができる
2つ目の利点として、自分の中で物事を判断する基準ができるところがあげられます。
1つの本を読み込むとその内容を覚え、やがて自分の中で1つの判断基準となります。
この判断基準を早い段階で作っておくと、以後似たようなを情報を見たときに自分の基準(本で学んだこと)と比べられるようになります。
これは様々な情報が散らばるインターネットを読み解く際に有効です。
「このネットにある記事は、自分が理解した内容と比べて…」といった具合ですね。
本が全て正しいわけではありませんが、インターネット情報の不正確さはそれ以上ですし、複数の人間の情報に触れると自分の中の基準がぶれやすいです。
経験上、はじめのうちは本でこの1冊と決めものを読み解いた方が、判断基準の形成が早いと感じます。
利点3.知らない情報に触れやすい
3つ目の利点として、知らない情報に触れやすいがあげられます。
逆説的な言い方ですが、インターネットは自分が検索した情報しか得られません。つまり精度の高い情報を得るためには、事前に自分がどれだけ情報(単語)を知っているかが求められます。
ギヤの調整をやってみたいなと思っても、最初のうちは「変速機(ディレイラー) 調整方法」などという検索ワードは思いつかないものです。
これに対して紙の本ならば、難しい単語を知らなくても何となく目的のページにたどり着くことができます。
上記の変速の話ならば、ぜんぶわかる!自転車メンテナンスでは8章に変速調整のページがあります。その章を開けば、どこかに自分の求める情報がある可能性が高いです。
自分の知らない調整方法やそれにまつわる専門的な単語も覚えることができるので、最初のうちは重宝すると思います。
これを繰り返すうちに知識量が増えていき、次第にインターネットでも適切な言葉で検索をかけられるようになります◎
利点を踏まえて本のレビュー
上記、紙の本を所持する利点について3つの理由をあげました。
私自身も自転車を触り始めた当初、本を購入しました。あれから随分と経過して、最近でこそ読まなくなりましたが、内容は血となり肉となっています。
参考になるかは分かりませんが、私の購入したぜんぶわかる!自転車メンテナンスのレビューを書いて終わりにします。
まず本の良かったことですが、知らない調整方法の存在や、それにまつわる専門単語を多く知れたところです。最初はちょっとした単語が分からないんですよね。
そういう意味では、この本には11章に自転車用語辞典がついていたのも良かったです。10P弱の簡単なものですが、当時の無知な自分は非常に参考になりました。
逆に悪かったことですが、一部、写真の写し方がよくないです。たとえば、ディレイラーの調整で写真が何を説明しているのか分かりづらいと感じるところがありました。
それとママチャリ(シティサイクル)の整備のことが載っていなかったのも少し残念でしたね。この本はスポーツ自転車が中心の内容です。
良い点、悪い点はありましたが、それらを指摘出来るようになるまで読んだのもまた事実です。個人的には満足な1冊でしたね。
まとめ
以上、紙の本を1冊所持して体系的に学ぶ、自転車メンテナンスの本を例にでした。
本には本の、ネットにはネットのよさがあります。ただ、最初のうちは本から体系的に学ぶと理解が早まると個人的には考えています。
パラパラめくっているうちに、思いがけない情報と出会えるのも紙の本の醍醐味です。図鑑や解説本の類は、できれば紙をおすすめしたいですね。
今回、私の所持する本を例としてあげましたが、押しつけるつもりはありません。
本というのは人それぞれ読みやすさが分かれます。なので、実際に大きな書店の自転車コーナーに行って、何冊か手に取ってみるといいですよ。
いい本を見つけたら教えて下さいね。

クロスカブ本体の改良
本体(JA45)購入 / 外装カバーの着脱 / リアキャリアの拡張 / リアボックスの追加【リアキャリア延長による加工も】 / ホムセン箱の改良(ボルトやフックの増設) / マルチマウントバーの増設 / スロットルアシスト / ナンバープレートに荷掛けフックを追加 / 2ポートUSB電源 / バーエンド着脱とスロットルパイプの交換 / グリップヒーター取り付け / バーエンドの交換 / サイドバッグサポート / パニアバッグ取り付け / 右サイドスタンド / エアバルブ角度の変更 / テールランプのLED化 / メーター球のLED化 / ウインカーリレー(LED対応)の交換 / フロントウインカーの小型化(続:LED化) / エンジンオイルの交換 /
クロスカブまわりの道具
バイクカバー / チェーンロック / ガソリン携行缶 / ヘルロックアシスト / ループワイヤー / スタンドホルダー /
身に着けるもの(ヘルメット、ジャケット、手袋etc…)
ヘルメット選び【SHOEI Z7】 (ヘルメット選び方) / インカム / グローブ3種【夏・春秋・冬】 / バイクジャケット / 脊髄プロテクターの追加 / ニーガードプロテクター / トレッキングシューズ / レインウェア